香りでつなぐ、日仏の感性と暮らし。
日本に帰国してから、「フランスが好きなんですね」とよく言われます。
たしかにそうかもしれません。でも正確に言えば、「フランスに流れる時間」や「暮らしの自由さ」に惹かれているのだと思います。
朝市で買った花を飾る。夕暮れ時にワインを開けて食卓を囲む。友人の家を訪ねたら、その人らしいインテリアや香りがある。南フランスでの日常は、決して贅沢ではないのに、心がふっとゆるむような「香りのある余白」に満ちていました。
そんな時間を、日本でも感じられるようなプロダクトを届けたい──
それが、2015年に真正ラベンダーのブランド「BLEU D’ARGENS(ブルーダルジャン)」と出会い、あっさんぷらーじゅを立ち上げた原点です。
あれから10年。
当社では、香りを“モノ”ではなく“文化”として伝えることを軸に活動を続けてきました。
そして今、3つの新たなブランドを迎え、4つの柱で「フランスの香り文化」をより立体的に紹介できるフェーズに入ろうとしています。
香りは、もはや嗜好品や贅沢の象徴ではありません。
それは、自分自身の価値観を暮らしの中で映す表現方法のひとつです。もっとも主観的で、もっとも実用的な自己表現とも言えるのかもしれません。
情報が溢れ、スピードが求められる現代において、日本の暮らしに、フランス文化ならではの「感性の余白」と「暮らしの軽やかさ」を提案していきたい。フランスの自由な発想と大胆さは、日本の丁寧さや繊細さと、美しく響き合うと感じています。
1本目の柱:BLEU D’ARGENS(ブルーダルジャン)との出会いと始まり



2014年、僕は学生としてフランス・ボルドーに留学していました。
勉強の合間に各地を旅するなかでフランス留学の最後に訪れたプロヴァンス地方で、初めてラベンダーという存在に出会いました。
最初のきっかけは、プロヴァンス地方の古都アルルの小さなマルシェ(朝市)でした。
チーズやオリーブオイルに並んで売られていたラベンダーのサシェや精油。「南フランスといえばラベンダーが名産」という事実を、南フランスの旅の一部として知った瞬間でした。
その後、留学最後の旅として再びプロヴァンス地方を訪れることにしました。もちろん目的は満開のラベンダー畑です。ちょうど開花の時期を迎えた広大な畑では、視界いっぱいに広がる紫と、甘い香りに集まるミツバチの羽音に包まれて、ただただ圧倒されたのを覚えています。
植物というより、もはや風景そのものに香りがついている——そんな体験でした。
そして2015年、帰国後に再び南仏を訪れるきっかけとなったのが、地方紙でたまたま目にした小さな記事でした。「在来種の真正ラベンダーを、ひとりの女性農家が復活させた」——その言葉に惹かれ、たどり着いたのが標高1400mに位置するBLEU D’ARGENS(ブルーダルジャン)農園です。
もちろん、ビジネスの知識も、貿易の経験もないまま、まずは動いてみようと決めたのが、あっさんぷらーじゅという会社のはじまり。20歳で渡仏、22歳の学生起業から始まった私たちの“香りの原点”であり、10年経った今も変わらぬ軸として存在しています。
3本の新しい柱 ── 香りから広がる「美とケア」の世界
ブルーダルジャンのラベンダーは、僕にとって香りとの出会いであり、すべての出発点でした。
しかし、フランスの香り文化はそれだけにとどまりませんでした。
土地に根ざした香りの多様性、美容というかたちで肌や髪に寄り添う香り、そして日常生活にそっと溶け込む香り——。10年の歩みのなかで、あらためて「香り」という文化と向き合ったときに出会ったのが、これからご紹介する3つのブランドです。
◆ EAU DE MENTON(オー・ド・マントン)



僕が初めてマントンを訪れたのは、2014年8月でした。
当時ボルドーに留学していた僕が、この街に惹かれた理由は2つありました。ひとつは、歴史あるクラシック音楽祭が開催されていたこと。もうひとつは、敬愛するジャン・コクトーの美術館があったことです。
そこで出会ったのが、マントンのもう一つの象徴——レモン。
レストランで食べたマントン産レモンの爽やかな酸味とほのかな甘み、そして上品な香り。
いまでも「人生で一番おいしかったレモンは?」と聞かれたら真っ先に思い浮かぶほどです。地中海の陽光と、イタリア国境の風土が育んだその香りは、極上のクラシック音楽とともに、五感すべてを刺激する体験として心に刻まれました。
それから11年。マントンには毎年のように足を運び、「いつかこの街の香りを、日本に届けられたら」——そんな思いが、ずっと心の片隅にありました。
そして2025年1月、とある展示会で出会ったのが「EAU DE MENTON(オー・ド・マントン)」。
戦後まもなく創業した老舗の香水ブランドで、マントンとニースの2店舗のみで展開するローカルブランドです。数年前にパッケージや香調を一新し、伝統と革新を兼ね備えた新しい姿で、マントンレモンの魅力を世界に発信しはじめていました。
まさか自分が、そのブランドの日本展開を任されることになるとは想定外。香りとフランス文化を軸に10年間活動してきた僕にとって、これは今回のフランス滞在の中でも、思いがけないビッグサプライズのひとつでした。
初めてマントンを訪れてから11年。
この夏、2025年8月に「EAU DE MENTON」はついに日本初上陸を迎えます。
南仏マントンの爽やかな風とレモンの香りで、皆さんの暮らしの中にも地中海のリゾート地のような軽やかな空間ができたら、これ以上嬉しいことはありません。
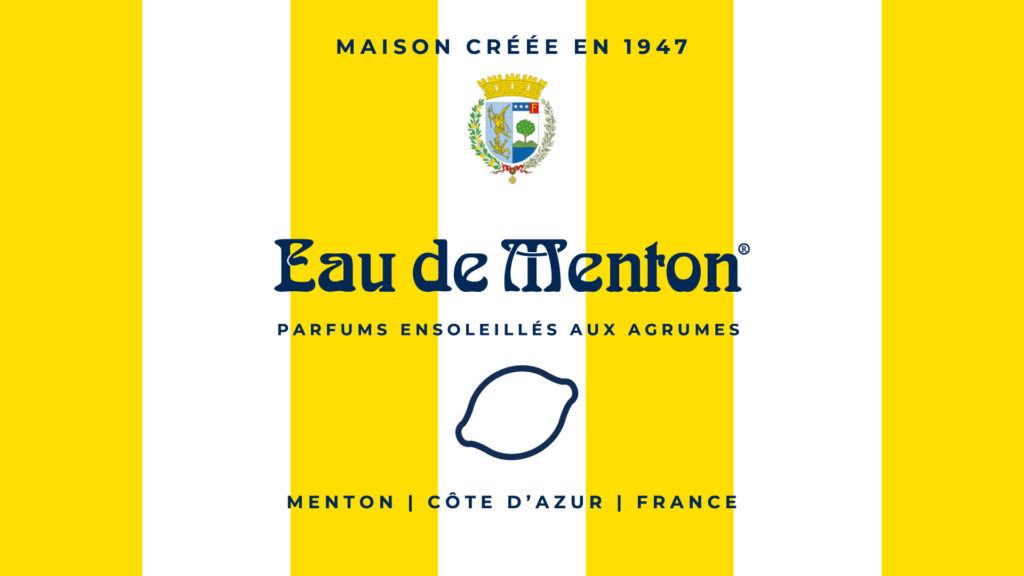
EAU DE MENTON(オー・ド・マントン)概要
マントン発、太陽と柑橘の香りをまとう香水。
「オー・ド・マントン」は、コート・ダジュールの小さな街マントンに拠点を置く、独立系の香水ブランドです。マントンは、南仏の陽光に包まれた“柑橘の楽園”として知られ、特に高品質なレモンの産地として世界的に評価されています。
1947年、創業者ルイ・ベルヌによって生み出されたのが、ブランドの原点となるレモンのオードトワレ「オー・ド・マントン」。厳選された高品質な天然レモンなど数種類の柑橘類を使用した香りは、その爽やかさと軽やかさから、当時のコート・ダジュールを訪れる映画俳優やアーティストたちの間でも瞬く間に人気を博しました。
創業以来75年以上にわたり、「オー・ド・マントン」は地元の伝統に根ざしながらも、常に現代的な感性を取り入れた香りづくりを続けています。ブランドの全製品は、今なおコート・ダジュールでひとつひとつ手作業で製造され、レモンをはじめとする南仏の自然の香りを大切に表現しています。
製品の97%が自然由来成分で構成され、ヴィーガン処方、詰め替え可能なガラスボトルを採用するなど、エシカルかつタイムレスな“香る喜び”を追求しています。
それはまさに、身につける人の気分をやさしく整える「香りの贅沢」。歴史ある香水でありながら、いまこの時代にもぴったりと寄り添う存在です。




◆ LAO CARE(ラオ・ケア)



グラースの香りを髪にまとう、プレミアム・ナチュラルヘアケア
ラオ・ケアとの出会いは、2024年2月。
僕が初めて「香水の都」グラースを訪れたときのことでした。
「100%天然由来成分で、髪のキューティクルを修復する特許成分を配合した新しいシャンプーブランドがある」——そんな話で友人から紹介されたのがきっかけでした。
グラース産の天然香料のみを用いた本格的な香り設計。さらに、「天然成分 × 最先端バイオテクノロジー」という組み合わせに興味を持ち、創業者リサの情熱もあって日本での展開を真剣に考えるようになりました。
実際に動き出したのは、2025年1月。製品の輸入に向けた手続きや、日本市場での使用感の検証を経て、同年2月に日本進出プロジェクトが本格始動しました。
このブランドの魅力は、ナチュラルな処方にとどまりません。EU初の特許を取得したキューティクル補修成分は、髪の内側から整えてくれるだけでなく、しなやかさとツヤをしっかりと実感させてくれるもの。さらに、香りはフランス・グラースの調香師が手がけた本格派で、髪にまとうフレグランスとしての完成度の高さにも驚かされます。
「髪が整うと、気持ちまで整う」。
そんな言葉がぴったりのケア体験を、毎日のバスタイムに届けてくれるのがラオ・ケアのプロダクトです。
そしてこのブランドを率いるのが、創業者でありCEOのリサ。27歳の女性起業家で、僕よりも若いながら並外れたビジョンと行動力を持つ、まさに次世代のアントレプレナーです。同世代の彼女とチームを組んでビジネスを進めていくのは、僕にとっても刺激的なチャレンジであり、新しいフェーズのはじまりでもあります。

LAO CARE(ラオ・ケア) ブランド概要
LAO CAREは、「香水の都」として知られる南仏グラースで誕生した、ナチュラル&サステナブルなヘアケアブランドです。植物の香りと生命力を最大限に引き出しながら、地肌と髪、そして心のバランスを整えるプロダクトを追求しています。
すべての製品は天然由来成分100%。防腐剤、合成香料、シリコンといった成分は一切不使用で、髪本来の美しさを優しく引き出す処方が特徴です。
香りは、まるで南仏の草花そのものを感じるようなピュアさを持ち、毎日のバスタイムを深いリラクゼーションへと導いてくれます。中でも特筆すべきは、ラオケアが持つ「香りの芸術性」です。香水の聖地グラースで培われた調香技術を生かし、髪にまとう香りとしての完成度を徹底的に追求しています。単なるナチュラルにとどまらず、感性に響く「プレミアムナチュラル」という新しい価値を提案する、今注目のブランドです。
日本では、公式オンラインショップ(近日公開)にて9月より先行発売予定。今後は百貨店でのポップアップイベントやホテルアメニティ、美容室での導入も予定しています。
香りで心を、最新の成分で髪を癒すケア。LAO CAREのある暮らしを、ぜひ体感してみてください。




◆ VINESIME (ヴィネジム)



2013年。
ワインに夢中になったのをきっかけに、僕はフランス・ボルドーへ留学しました。
学業の合間を縫って各地を旅する中で、留学最後の旅に選んだのが前に触れたプロヴァンス地方のラベンダー畑とブルゴーニュ地方のワイナリーでした。ラベンダー畑に感動した後に待っていたのは、飲んだこともないのに名前だけは必死に覚えた有名な村。ヴォーヌ・ロマネ、ジュヴレ・シャンベルタン、ラ・ターシュ——。名前だけでテンションが高まる特級畑(グランクリュ)を、まるで巡礼のように歩き回ったのを覚えています。
澄んだ空気、広がるブドウ畑、ひっそりと佇む石造りの看板。
そのひとつひとつが、五感に刻まれるような体験でした。
それから8年後の2021年。
思いがけないご縁から【VINÉSIME(ヴィネジム)】というブランドのテストマーケティングを日本で担当する機会をいただきました。
ワイン用ブドウに含まれるポリフェノールや、ブルゴーニュ地方特産の黒カシスの新芽など、ワイン文化に根ざした成分を使ったスキンケア——というコンセプトに、直感的に惹かれたのを覚えています。香り、テクスチャー、そして「土地の力を肌に届ける」という哲学。すべてに共感し、このブランドの世界観を日本で伝えたいと思うようになりました。
その後、2024年にフランス本国のチームとの契約交渉が本格的にスタート。フランス滞在中の2025年2月、ヴィネジムの日本総代理店としての展開を正式に担うこととなりました。
ワインをきっかけにフランスに渡り、ワイン由来のスキンケアを届ける——。
当時の僕には想像もできなかったストーリーが、10年越しでつながった瞬間でした。
そしてもうひとつの偶然。
実は僕が1年3ヶ月暮らしていた南仏ニースの老舗五つ星ホテル「ル・ネグレスコ」のスパでも、このヴィネジムが採用されていたのです。まさに縁が重なったとしか思えない出来事でした。

VINESIME(ヴィネジム) ブランド概要
VINÉSIME(ヴィネジム)は、フランス・ブルゴーニュ地方に広がるグランクリュ(特級畑)で育まれたワイン用ブドウや、黒カシスの新芽など、土地固有の植物資源を活かした“ヴィノ・コスメティック”の先駆け的ブランドです。
自社開発の美容成分「A2OC」は、ブルゴーニュの名門ワイン生産者と提携し、オーガニック栽培されたピノ・ノワール種の果皮・種子・果肉から抽出されるポリフェノールと、ブルゴーニュ名産の黒カシスの濃縮エキスを融合した独自の複合成分。肌の酸化ストレスに対し、高い抗酸化力と再生力を持ち、年齢とともに揺らぎやすい肌に根本から働きかけます。
香りの設計にもブルゴーニュの風景が息づいており、深みと透明感を持つ「ワインのようなスキンケア」という表現が最適。製品はすべて、フランス国内で製造され、クリーンビューティーの基準を満たす処方で仕上げられています。
高級スパや五つ星ホテルでも導入されており、ただのスキンケアにとどまらず、「ブルゴーニュワインの魅力を五感で感じる」体験として、心と肌の再生をサポートします。




4. 今後の展開
あっさんぷらーじゅは、創業から10年間、ブルーダルジャンの真正ラベンダーを通して、「香りのある暮らし」の価値を丁寧に届けてきました。
一方で、フランスにはまだまだ魅力的な植物や香りが沢山あることも知っていました。
——フランスの香り文化には、もっと多面的で、もっと自由な表現の可能性がある、と。
今回、日本での展開が始まる3ブランド(EAU DE MENTON、LAO CARE、VINÉSIME)は、いずれも「香り × 美容 × ライフスタイル」を軸に、土地の記憶や植物の力を宿した製品たちです。
この4ブランド体制によって、スキンケア・ヘアケア・フレグランスという多様な分野を横断しながら、香りと美容を融合させた日仏の架け橋を築いていきたいと考えています。
現在の日本社会は「余白」「余裕」といったものが薄れてきているように感じています。フランスの香りを通して自由な価値観や哲学、さらには「本来のラグジュアリー」をお伝えできたらと考えています。
これからはオンラインショップを中心にしつつ、ポップアップイベント、百貨店・セレクトショップ・スパ・ホテルでの展開を通じて、香りそのものだけでなく「香りがもたらす価値」も一緒にお届けします。
今回、弊社にて展開するすべてのブランドは、ただの香りではなく、心のスイッチをそっと押してくれる存在となりうる上質な香りです。そこには記憶と感情に寄り添い、暮らしの中に「感性の余白」を取り戻してくれるような体験が生まれます。それはまた、自分の意見を持つこと、自分の感情や感性、そして、五感を信じて暮らすことの大切さを思い出させてくれるのかもしれません。
単なる輸入商社ではなく、香りと文化を届けるストーリーテラーでありたい。
そんな思いを持って、これからも「フランスの香り文化」の魅力を、日本の暮らしに提案してまいります。


